
H19.8.27夏の集い 講師:野村 亨
--- 目 次 --- 1.国連の「ミレニアム生態系アセスメント」 (1)ミレニアム生態系アセスメントの概要 (2)主要な四つの結論 (3)四つのシナリオによる生態系と人間福利の将来像 (4)問題点と今後の対策 2.顕著な生態系の負異変について (1)絶滅危機動物種の増加 (2)土壌・地下水汚染 3.地球破滅を回避するための動きと提案 (1)生態系の経済価値に関する図書 (2)森林認証制度の推進 (3)林業の動向と活性化についての提言 (4)次世代へ健全な生態系の伝承義務
平成17年2月7日の日経新聞に「生態系破壊 人間が加速」の記事が掲載された。森林が40年間で14%消失、生物種絶滅速度1000倍という衝撃的な見出しで、国連が実施したミレニアム生態系アセスメントの報告書の紹介であった。
技術革新により最近の50年間に人間社会経済は著しく高度化した。また人口増加に伴い入植居住地造成及び食料生産のための農地形成に森林伐採が進み、一方、工業用希金属採取の地下資源採掘などで、生態系の破壊現象が顕著になってきている。生態系バランス機能の低下により生物の生存・維持ができなくなる危機感から、生態系の回復・保存について関心が高まっている。今回、国連が実施した「ミレニアム生態系アセスメント」もその観点から実施されたと推測される。
(1)ミレニアム生態系アセスメントの概要
生態系の変化が人間社会に与えている負の現状を調査・把握し、改善をめざして対処すべき方向を示すため、科学的情報を提供する国際的プロジェクトで、2000年から5年間にわたり95カ国1,360人の科学者によって実施された。
生態系には、食料や水などの供給、気候や病気などの制御、レクリエーションなどの文化的便益、土壌生成や物質循環など24の機能がある。調査の結果、24項目の中で15項目の多くが低下しており、このまま推移すると人間社会の存続に重大な影響が出ることを提示している。
(2)主要な四つの結論
①過去50年間に人類が行った生態系改変が、地球上の生物多様性面で莫大な非線形的喪失をもたらした。
②人間社会の経済発展は生態系の改変で達成できたが、反面生態系サ-ビスの劣化、急激なリスクの増加、貧困層の増加等のマイナス面が創出され、将来世代が得る利益が大幅に減少すると予想される。
③生態系サ-ビスへの需要の増大に対応しながら、生態系の劣化を回復させるには、政策・制度・実践において大幅な変革が必要である。
(3)四つのシナリオによる生態系と人間福利の将来像
生態系の改変要因と生態系サ-ビスの変化の様相は不確実であるので、定量モデルと定性解析の二つの手法によって検討した。現状とその傾向によって以下の四つのシナリオが作成され、工業国と発展途上国別に物質的福利、健康、安全、社会関係などの機能が ●増加・向上 ●2000年と同水準 ●減少・劣化の三つに分けて予測している。
①世界協調(Global Orchestration)シナリオ
世界貿易と経済の自由化に焦点をおいて、全世界協調一体化した社会形成
②地域別管理体制(Order from Strength)シナリオ
地域市場が重視されている現状からの延長社会
③順応的モザイク(Adapting Mosaic)シナリオ
流域レベルでの生態系に焦点をあてた政治・活動が行われ、生態系の地域管理社会形成
④テクノガ-デン(Techno Garden)シナリオ
環境に調和した技術により地球全体を高度管理し、人為的に操作された生態系を利用する社会形成
以上の四つのシナリオによる世界人口の2100年予測は、現在63億人であるのに対して ①世界協調シナリオでは64億人 ②地域別管理体制シナリオでは100億人< ③順応的モザイクシナリオでは100億人 ④テクノガ-デンシナリオでは83億人と予測している。
(4)問題点と今後の対策
各国の生態系評価システムは乖離が大きく、相互比較可能な時系列情報が欠落している。今後、相互に関連性を持たせた定量的モデルの作成と相互承認が必要である。更には各国の生態系保全の必要性の共通認識と協調した保全活動が必須条件である。
(1)絶滅危機動物種の増加
IUCN(国際自然保護連合)日本委員会発表による「レッドリスト2006」によると、絶滅の危機にある動物種数は前回の数値よりも更に増加しており、1990年の報告値との増加数倍率は下表のとおりで種別により差異がある。
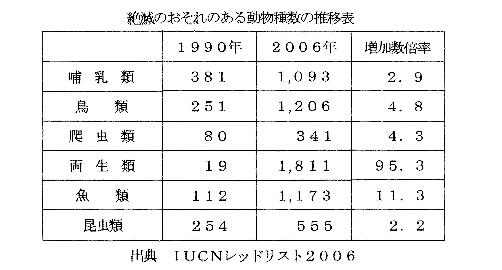
動物種類の消失の最大要因は森林伐採などによる生息地の消失である。地球上に生存している人間を含め総ての動物は、捕食・摂食の食物連鎖によるエネルギ-源の取得・共生の生態系バランスにより生命が維持されている。生態系の構成要素と相互の関連は以下のようになっている。(出典:生き物の科学と環境の科学)
各ランクの生物数がランスしていれば、全体の生物生命が維持存続できる。動物の食物連鎖では、餌となる下位生物のエネルギ-総量は上位生物の10倍存在している。
海洋でも同様の法則が見られ、光合成によって植物性プランクトンが発生し、動物性プランクトンの餌となり、上位のオキアミ→鰯→サバ→マグロへとエネルギ-層が形成されていく。ハマチ10㎏の養殖には、餌となる鰯・サンマが100㎏必要が必要であり、エネルギ-ピラミット10倍の法則が証明されている。
(2)土壌・地下水汚染
①地下金属資源採掘・精錬及び生産工場の有害物質含有排水の放流、農業における化学肥料・殺虫剤散布などで、有害重金属の直接地下水への流入による。発展途上国ではこの汚染が進み、ヒ素などの有害金属含有量が多くなった地下水を飲料にしていることから、住民特に乳幼児の死亡率が高くなっている。
②従来地層内に蓄積していた重金属が採掘や建設工事により撹拌され、地下水に溶出し汚染が発生する。先進国においては工場跡地を再開発する際の土質調査により土壌・地下水汚染が明るみにでて社会問題になっている。
(3)森林資源の急速な減少
我が国の現状(平成18年版森林・林業白書による平成16年度実績)木材消費量は8,980万m3で、その内容は国内材比率18.4%、輸入材比率が81.6%(パルプチップが全体消費量の35.2%)
日本の森林面積率は67%で世界トップであるが、木材成長量 8,000万m3/年の木材資源があるのに、輸入材が多く生産量<消費量となっている。